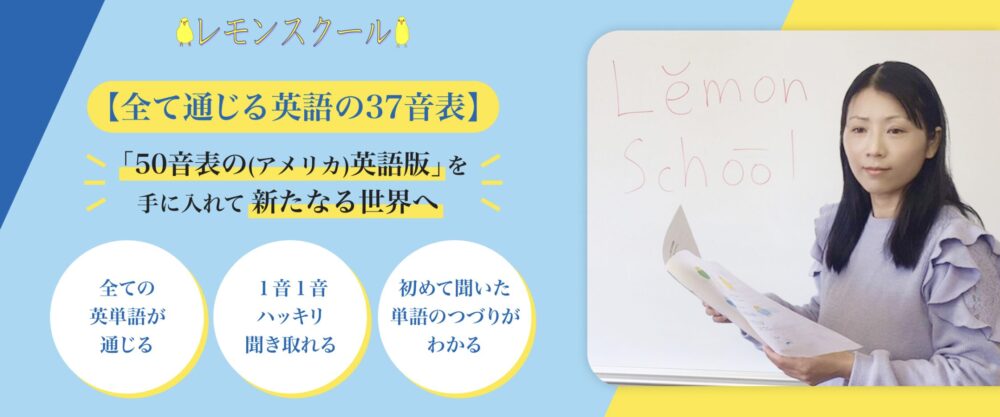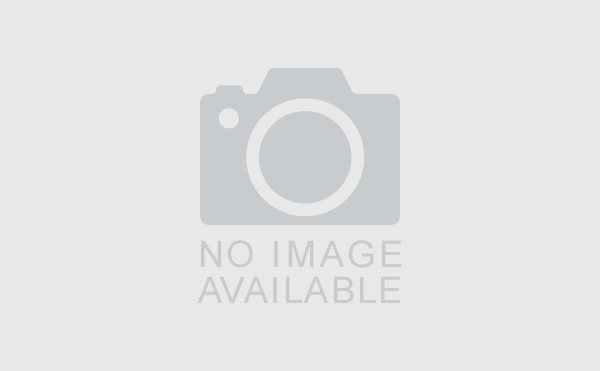SoundSpel(読み通りのつづり)に関する面白いブログを見つけました。
SoundSpelという、読み通りのつづりに関して色々と記事を書いている方のブログを見つけました。ようするに、発音リスペリング(pronunciation respelling)と同じことです。こういうことの啓蒙活動をしている方を見るのは、私としては非常に嬉しいことです!
→よみかたエイトさん
こちらのサイトに貼ってあった、SoundSpelWurdListも必見です。
具体的にどういうことかというと、上記のサイトhttps://americanliteracy.github.io/ts/soundspel/をそのままコピペすると
IN SOUNDSPEL, WORDS ARE SPELLED AS THEY SOUND.
- hat, have, laugh, plaid
→ hat, hav, laf, plad - red, head, said, friend
→ red, hed, sed, frend - herd, earth, birth, journey
→ hurd, urth, burth, jurny - roll, hole, soul, goal, bowl
→ roel, hoel, soel, goel, boel - tough, love, judge, tongue
→ tuf, luv, juj, tung - phone, city, gorgeous
→ foen, sity, gorjus - knight, receipt, asthma
→ niet, reseet, azma
GETTYSBURG ADDRESS IN SOUNDSPEL
Foerscor and seven yeers ago our faathers braut forth, on this continent, a nue naeshon, conseevd in liberty and dedicaeted to th propozishon that all men ar creaeted eeqal.
Now we ar engaejd in a graet sivil wor, testing whether that naeshon, or eny naeshon so conseevd, and so dedicaeted, can long enduur. We ar met on a graet batl-feeld in that wor. We hav cum to dedicaet a porshon of that feeld, as a fienal resting-plaess for thoes hoo heer gaev thaer lievs, that that naeshon miet liv. It is aultogether fiting and proper that we shuud do this.
But in a larjer senss we cannot dedicaet, we cannot consecraet, we cannot halo this ground. Th braev men, living and ded, hoo strugld heer, hav consecraeted it far abuv our puur power to ad or detrakt. Th wurld wil litl noet, nor long remember, whot we say heer, but it can never forget whot thae did heer. It is for us th living, rather, to be dedicaeted to th graet task remaening befor us that from thees onord ded we taek increest devoeshon to that cauz for which thae gaev th last fuul mezher of devoeshon – that we heer hiely rezolv that thees ded shal not hav died in vaen, that this naeshon, under God, shal hav a nue burth of freedom, and that guvernment of th peepl, bi th peepl, for th peepl, shal not perrish frum th urth.
こういうものを、日本の英語教育で紹介していくことは、非常に大事だと思います。
一方で、既に英語の音やつづりがわかっているネイティブには、こういう書き方は良いですが、私たちのように英語の音もつづりもわかっていないノンネイティブには、もう1段階簡単にする必要があるでしょう。特に以下の3点です。
● 例えばnaeshon (nation)のshonや、continentのnentのような、強勢のない母音(私は軽音と呼んでいます)が、音ベースではなく、元のつづり通りになっているので、ノンネイティブ(日本人に限らず)には、shun, nuntのように読み通りにした方がいいでしょう。
● 例えばnaeshon (nation) のnaeや、hoel (hole)のように、二重音字(2文字で1音を表すもの、子音のshやchも二重音字)を、実際に日本人に教えてみると、人によっては苦戦します。
印象として2〜3割くらいの人は簡単に何の抵抗もなく習得するのに対し、7〜8割くらいの人は、結構苦戦します。その7~8割の中の1割くらいの人は、「こんなのは受け入れられない!」くらいの感じで大苦戦します。私は学習者としてはラッキーなことに、すんなり受け入れられる2〜3割に入っていたので、逆に指導者としてはアンラッキーなことに、これを受け入れられないほどに悩む人たちの気持ちを理解するのに苦労しました。そこで、naeはnā、hoelはhōlというように、1文字1音にして補助記号を付けることにしたら、みんなウソのように驚くほどすんなり受け入れてくれました。
● 方言を一つに絞り、例えばfaathers (father)のaa、brautのau (brought)、onのoの3つを全て発音上の区別するアメリカ人やカナダ人がいるかどうかはわからないので(アメリカ人やカナダ人の社会言語学者達に聞いてもわからなかった)、これら3つのうちの2つだけを区別する、または3つとも全部同じ音にするという大多数の人の方言通りに表記する方がいいでしょう。日本人がこの3つを区別する必要は全くないと思います。