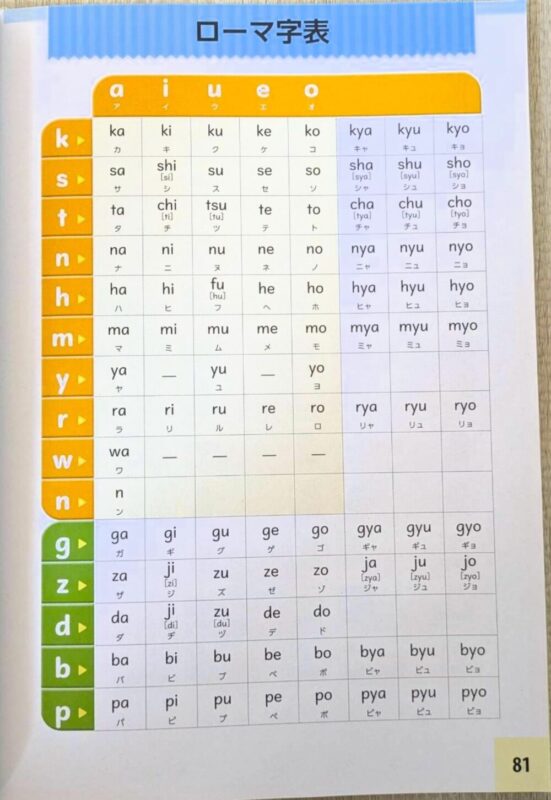園田大志先生の「英語イントネーションの教科書」で勉強しました。レビュー
英語講師たいし(大志)先生こと、園田大志先生の、イントネーションの解説書、「英語 イントネーションの教科書」
を学ばせていただきました。そのレビューを、私の経験も含めて書きたいと思います。

まずこの教材は、初級者から上級者/指導者まで、全レベルの方におすすめだと思います。
初級者の方は、わかる部分だけしっかりこなしていき、難しい理論の部分は無理に理解する必要はないでしょう。
中級以上の方は、逆に難しい理論の部分が、非常に役に立つと思います。
さて私は、音素、音節、強勢、声調といった、
単語の弁別(間違えると単語の意味が変わってしまうもの)に関係するものを重視してきましたが、
実を言うとイントネーションに関しては、日本語、英語、中国語のどれに関しても、
そこまでちゃんと勉強するチャンスがありませんでした。
もちろんミナ表作成にあたって、バナナさんの韓国語の音声を担当していただいた埼玉大学のソヌ・ミ先生から、
イントネーション全般に関してアドバイスはいただきましたが。
発音系の学会でも、イントネーションに関するリサーチは少なく、やや影が薄い印象を受けます。
中国語の授業でも、音素、音節、強勢、声調は徹底的に教えてもらえますが、
(四声を区別する音節には強勢, stressがあり、軽声の音節はunstressedと私は考えています)
イントネーションの指導はあまりしてもらえません。
そこで今回、Xでお世話になっている園田先生の「英語 イントネーションの教科書」で勉強させていただきました。
大抵の英語の発音教材では、いわゆる核音調という、センテンスの最後部分のイントネーションの説明しかありません。
例えば、
I’ve been waiting a long time for a vacation. (私は休暇をずっと待っている。)
の場合、通常はvacationのcaの部分に音調核があり、その音調が核音調になります。
確かに最も大事な文法的な情報は、この核音調が担っているので、
最低限この部分のイントネーションさえ正しければ、意図は伝わります。
だから、大抵の英語の発音教材ではここだけを教えることが多くなります。
しかし実際にしゃべったり、音読したりする時は、I’ve been waiting a long time for a va…
の部分にも当然イントネーション(音程)はあるので、何か音程をつけなければいけません。
むしろ、日本人に難しいのはこの音調核より前の部分です。ここを知りたいのです。
音調核以降は、ネイティブの英語を注意深く聞いている人なら、結構感覚でわかってしまうものですから、
それほど習っても、新情報という感じはしないと感じている方も、少なくないのではないでしょうか。
しかしこの音調核より前の部分を、私は体系的に教わったことはなかったので、
独学でやるしかありませんでした。
大学の英語音声学の授業を担当していたので、独自の方法で教えてはいましたが。
しかし、「英語 イントネーションの教科書」では、音調核より前の部分がかなり徹底的に説明されています。
これは非常に助かります!
また、よくこの部分のうち、最初の重音(強勢のある所)以降を頭部(head)と言いますが、
この本によるとアメリカ英語に頭部の概念があてはまるかどうかわからないようです。
実は私もそのように感じていて、頭部という概念は使っていませんでしたが、
もし私の解釈が間違っていなければ、それもあながち間違っていなかったようで、よかったです。
もちろん頭部の考え方でしっくりくることも多々ありますが、
実際にはもっと複雑に動いていることもあるということです。
また、教材によっては、例えば説明では上昇調(rise)と言っている/書いているのに、
実際の音声は下降調(fall)だったり平坦調(level)だったり、というように、
説明と音声が合っていない教材も意外に珍しくありませんが、
「英語 イントネーションの教科書」では、説明と音声が違うということがありません。
非常に音声が正確で、学習者が混乱することがありません。
またこの教材では、理論がしっかりしている上に、例文が非常に多いので、
例文をたくさん練習しているうちに、ルールを自然に身につけていく感覚があります。
ルールから学ぶのが得意な方も、数をこなして感覚を身につけるのが得意な方も、
私のようにその両方が必要なタイプも、どのタイプでもうまく身につけられそうです。
理論の面でも、TragerとSmithといった、日本でいうなら金田一春彦や服部四郎くらいの時代の、
伝統的なアメリカの音声学の文献を引用しているあたりも好感が持てます。
原点に帰って、古い文献を参考にすることは非常に大事だと思います。
また、園田先生の英語の発音が非常に上手いので、
日本人英語学習者として、目標、ロールモデルの1人にできると思います。
この教材は、アメリカ英語にもイギリス英語にも対応できるようになっています。
ここも素晴らしいと思います。
ただ園田先生はイギリス発音が得意な方のようなので、
「アメリカ風の発音」と書いてあっても、イギリスっぽいイントネーションに聞こえることもあります。
(母音と子音はアメリカ式です。でももしかしたら本書でいう「滑音」という同じ音節内で音程が変わるものが、
特に多音節語でアメリカ英語にしては急だからかもしれません。
などという批判を、私のようにイギリス英語の発音のデモンストレーションを避けている人間にされたくないでしょうが、、、)
とにかく、色々勉強になったと同時に、私ももっと頑張らなければという気になり、
インスピレーションをいただきました!