いろいろと初めて学ぶことが多く、とても興味深く学習しています!
24子音表についての質問ですが、閉鎖音と摩擦音で、有声を上の位置、無声を下の位置にした理由は、何かあるのでしょうか?
感覚的には、無声がベースで、それに声を出して有声にする感じなので、無声が有声の上にあった方が個人的には分かりやすい感じがしました。(発音練習の「ffffffffffffffvvvvvvvvvvv」のイメージです。)
(追記) 横軸が、唇(前)→ のど(後)と、位置の変化を表しているというのは、興味深かったです。
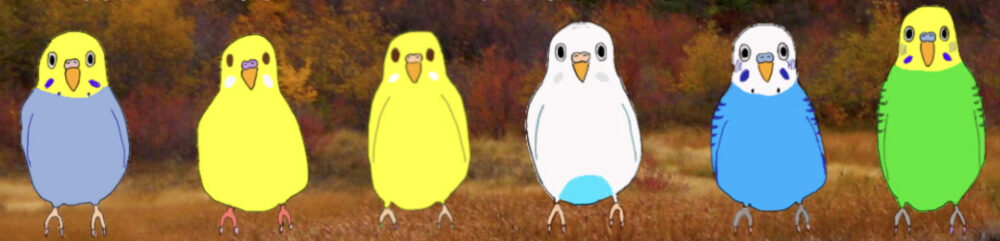
全て通じる英語の37音表の内容や、発音全般に関する質問がありましたら、お書き下さい。
初心者の方の質問も大歓迎なので、「こんな初歩の質問をするのは恥ずかしい」と思う必要はありません。
基本的に講師であるレモンがわかる範囲で回答しますが、皆様同士でも積極的に意見交換をしたり、悩みのシェアをしていただけると、楽しくなると思います。
※皆様が気持ちよく使えるように、個人情報(電話番号、メールアドレス、口座番号など)、法令違反(犯罪予告、著作権法違反、プライバシーの侵害など)、わいせつや暴力的な内容、過度な批判や誹謗中傷、特定の民族や地域等に対する差別的な内容は、禁止とします。
スパムを防止するために、大変お手数ですが、投稿するためにアカウントの作成をお願いします。(5分もかからないと思います。)
※質問を投稿する際に、「この掲示板を購読する」にチェックを入れないと、投稿ができない場合があります。ご不便をおかけして申し訳ありません。
いろいろと初めて学ぶことが多く、とても興味深く学習しています!
24子音表についての質問ですが、閉鎖音と摩擦音で、有声を上の位置、無声を下の位置にした理由は、何かあるのでしょうか?
感覚的には、無声がベースで、それに声を出して有声にする感じなので、無声が有声の上にあった方が個人的には分かりやすい感じがしました。(発音練習の「ffffffffffffffvvvvvvvvvvv」のイメージです。)
(追記) 横軸が、唇(前)→ のど(後)と、位置の変化を表しているというのは、興味深かったです。
ご質問いただき、ありがとうございます。(返事が遅れてしまい、すみません。)
> いろいろと初めて学ぶことが多く、とても興味深く学習しています!
そう言っていただけると、レッスン動画を頑張って作った甲斐があります。ありがとうございます。
> 閉鎖音と摩擦音で、有声を上の位置、無声を下の位置にした理由は、何かあるのでしょうか?
実を言うと、最初は、b, d, f, g, h... というように、アルファベット順に並べていたのです。
しかしこれだと音声学的にまとまりがないので、閉鎖音と摩擦音と共鳴音という3つのグループに分けることにしました。
ただ元々b, dから始まっていたために、つい新しいバージョンも、b, dから始めた結果、有声が最初に来ることになってしまいました。
> 感覚的には、無声がベースで、それに声を出して有声にする感じなので、無声が有声の上にあった方が個人的には分かりやすい感じがしました。(発音練習の「ffffffffffffffvvvvvvvvvvv」のイメージです。)
ご指摘ありがとうございます。はい、全くおっしゃる通りだと思います。人間の口や喉の仕組みからも、無声の方がベースで、有声はそれにプラスアルファーの動作を加えたものです。
その証拠に、英語では摩擦音も有声と無声がありますが、東京の日本語には有声の摩擦音は基本的にはありません。「ざ」「じ」は破擦音なので、音的には「づぁ」「ぢ」が有声になったものです。
中国語でも、無声の摩擦音f, s, shはありますが、それに対応する摩擦音がありません。中国語のz, zhは破擦音です。
つまり、ベースの音はあるけど、それにプラスアルファーの動作を加えた、より複雑なものが無いということになります。
だから、無声を上にした方が、理にかなっているし、わかりやすいでしょう。
(論文で音の一覧表に必要性について書いた時にも、有声を上にしてしまっていますが、誰も指摘してくれる人はいなかったので、助かりました。)
子音一覧表が載っている動画が多いので、すぐに修正はできませんが、余裕ができたら変更しようと思います。
>(追記) 横軸が、唇(前)→ のど(後)と、位置の変化を表しているというのは、興味深かったです。
よかったです。