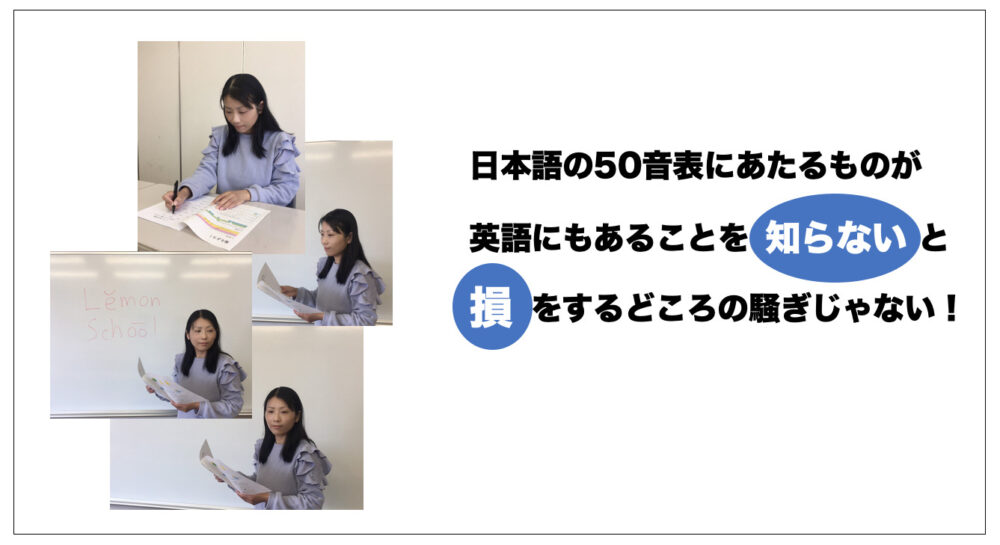トピック一覧
● World Englishesとジャパニーズイングリッシュ
● World Englishesは、発音指導が苦手な教員の口実になる?教員の辛い立場
● 正しい発音を導入すると、英語教員の発音が間違ってることがバレて困る。教員も生徒もハッピーになるには?
● [ə]と[ʌ]の区別を英語ネイティブはできない。[ə]と[ɪ]も区別できない:発音記号の本当の読み方
● 「発音記号」から「発音リスペリング (pronunciation respelling)」へ
● 世界の英語変種に対応するために、逆に1つの方言の発音をしっかり習得しよう!
作者:野北明嗣
英和辞典や発音教材には、発音記号がズラリと並んでいて、ものすごく難しそうに見えるでしょう。母音だけで26個以上あったりします。ですが、安心して下さい。英語ネイティブは、そんなに多くの母音を区別していません。
まずその26個以上の母音には、ダブっているものがいくつもあります。これらを削れば整理できます。また、方言差が考慮されているため、実際の1方言の音よりも多くなっています。これはどういうことかというと、日本語で例えるなら、簡単に言えば東京と大阪の発音を両方載せたら、当然たくさん音があるように見えますが、実際は東京の人はそんなに多くの音を区別していない、というようなことです。野北明嗣. (2018). 英語の全音素一覧表の提案: 発音体系の全体像を把握させる教育. 外国語外国文化研究, 28, 30-45.
とは言っても、英和辞典、特にジーニアス第5版などの編集者の方達は非常に発音記号にこだわっていて、職人のこだわりを感じることができます。一方、中学英語教科書の発音記号は、少ないスペースに英米両方の発音を載せようという欲張ったことをしている上に、難しい記号を避けようとして、結果として違う音に同じ記号を使ったり、同じ音に違う記号を使うことになり、「解読」するのに相当な知識が必要になります。その上、許容範囲を超える量のミスプリが見つかったりします。中学英語教科書の発音記号は、中学生どころか、英語音声学を教えている音声学の研究者ですら「解読」できない場合がたくさんあります。なので英語教員のみなさんも、是非胸を張って「私は発音記号なんて読めません」と公言して下さい。発音記号を読ませたいのなら、まずユーザーのことを考えて記号をもっとユーザーフレンドリーにし、その体系的な指導マニュアルを作らなければいけません。発音の研究者である私も解読できるようになるまで、相当な年月がかかりました。今もまだ勉強中です。そのことを、こちらの論文でまとめたので、よかったら読んで下さい。
野北明嗣 (2022). 中学英語教科書の発音記号に関する音声学者の混乱の調査:発音記号の見直し. 外国語教育研究 25, 206-222
数年前に、神田外語グループの「教科書にのっていない世界の授業」で、栗本孝子先生の発音の講義を受けさせてもらいましたが、もうほとんどは発音記号の現状に関する愚痴でした。あまりに共感できて、最高の講義でした。発音指導に本当に熱心な先生方は、このように発音記号に対しやきもきしています。
よく「発音記号をちゃんと見ろ」とか「発音記号くらい自分で読めるようにしろ」という声も聞きますが、こういうことを言う人たちは、残念ながら発音記号を正しく読めていない可能性が高いでしょう。前述の通り、発音記号はとても独学でできるような代物ではありません。もちろん独学で読もうとする勤勉な人たちも少なからずいるのですが、皮肉にも間違って解釈してしまうので、読めているつもりでも実際には読めていないのです。私もそうでした。発音記号は相当取り扱いに注意しなければいけません。発音記号を読めているつもりでも読めていない例はこちらです →峯松先生の相互シャドーイング
それでも発音記号を読みたいという方は、
1) まず音声学の基礎をしっかり勉強して、母音の仕組み、子音のしくみを理解します。これを知らないと、発音記号を使うメリットがほぼありません。英語ネイティブがやっているような、発音リスペリング(pronunciation respelling)という「読み通りのつづり」を使った方が断然良いです。私が昔勉強した音声学の本は、小泉保 (2003) 「改訂 音声学入門」大学書林です。
2) それと同時に、発音リスペリングを使って、英語の母音や子音がいくつあるのか、全体像を把握します。その時、まず、アメリカ英語かイギリス英語かどちらかの、どこか1つの方言をある程度のレベルで身につけます。決して同時に色々手を出そうとしてはいけません。ネイティブの知り合いに生の音声を発音してもらいましょう。1つしっかり身につけた上で、幅を広げていきます。
3) まずどこか1つの方言の全ての音素を把握して、自分でもある程度発音したり聞き取ったりできるようになったら、最後に、それぞれの音素に慣例的に使われている記号を把握します。 日本とアメリカとイギリスでは記号が違うので、そのあたりも注意です。
発音記号をちゃんと読めるようになるには、この手順をしっかり踏まなければいけません。一朝一夕に身につくものではありません。でも、それでもやりたいという人は、大歓迎です!
それを踏まえたうえで、本題の[ə]と[ʌ]ですが、ここではそのような手順を踏まなくてもできる応急処置的な技を紹介します。この二つの記号の違いがわからないという人が多いでしょう。でも安心して下さい。両者は英語ネイティブにとっては同じ音です。特に音声学を知らない英語ネイティブにとっては、全く同じ音です。区別する必要はありません。
英語の発音では、強勢というものがすごく大きな役割を担っていて、この概念を理解するのに私を含む日本人は非常に苦労します。音声学では、しばしば日本語のアクセント核と、英語の強勢が混同され、私も大学院生の頃は混同していましたが、両者は全く別物です。例えるなら、蝶々は外見は鳥に似ていますが、蝶々を鳥類だと扱ってはおかしいのと同じです。強勢に関してはまた別な機会にお話しします。その強勢がある時は ʌ の記号を使い、強勢が無い時は ə の記号を使うというだけです。
例えばScholastic Pocket Dictionaryという英語ネイティブ用の辞書では、両者は区別しておらず、どちらも uh と表記されています。この uh という表記は絶対に覚えておいた方が、より英語を楽しめます。しかも、Merriam-Webster.comという辞書では、ʌ という記号を使わず、ə しか使っていません。Hammond (1999) The Phonology of Englishも参照。
音韻論的には、音素/ʌ/の異音として、強勢があれば[ʌ]、無ければ[ə]、という考え方もできますが、強勢がない時の音価にはかなりばらつきがあるので、本当に単純に[ə]と書いて良いのか?という疑問があります。なので、「強勢がある時は ʌ の記号を使い、矯正が無い時は ə の記号を使うのが慣例になっている」という程度の方がいいでしょう。
ちなみに、ただの英語ネイティブではなく、英語ネイティブの音声学者に、[ə]と[ʌ]を発音しわけてほしいとお願いしたら、「単独だと発音しわけられないから、単語の中ででもいい?」と言われました。英語ネイティブの音声学者でも発音しわけられないのです。ただし、「両者は違うんだ」と主張する英語ネイティブの音声学者もいるということも、付け加えておきます。これを知っていればまたより深く理解できます。
また、両者を区別しなくていいと言ったら、「[ə]は「え」に聞こえるから、区別すべきでは?」と日本人の音声学者から言われたことがあります。確かにその通りです。面白いことに、[ə]が「え」に聞こえる場合は、英語ネイティブにとっては、[ɪ]と区別がほぼできないということも、英語ネイティブの音声学者達から聞きました。ちなみに[ɪ]は、決して「い」と読むのではなく、「え」に近いです。
そこで基本的に ə と辞書に書いてある場合、単語の最後だったら ʌ と同じ。それ以外だったら大抵 ɪ と同じに発音しておけば、問題ありません。また、əl だったら ʊl、そして ər だったら北米英語なら ɚ です。əl を ʊl と読むことは、音声学を知らない英語ネイティブから習いましたが、音声学を知っている英語ネイティブは認めない人が多いことも知っておくといいでしょう。
では、具体例とともに、以下にまとめてみました。まずは難しく考えず、赤い太字のとこだけ見て下さい。それで余裕ができたら他を見て下さい。
● 単語の最後の ə は、ʌ と同じ。ほぼほぼ日本語の「あ」。例)Russia /rʌ́ʃ.ə/ ロシア → これらの ʌ と ə は同じ発音。tundra /tʌ́n.drə/ 凍土帯、ツンドラ → これらの ʌ と ə は同じ発音。
● Lの前の ə つまり əl は、ʊl と同じ。例) pencil /pɛ́n.səl/ えんぴつ → əl は、ʊl と同じ。people /píː.pəl/ 人々 → peopleのpleと、pull /pʊ́l/ は同じ。 family /fǽm.əl.li/ 家族 → この ə も ʊ で良い。(fam.lyと2音節でも良い。)
● 北米英語では、r の前、つまり ər は ɚ というか、1音節カウントする r。例)correct /kə.rɛ́kt/ 正しい → 母音を入れずすぐ r を発音する。ただしそこで1音節カウントすることが大事。
● それ以外の ə は、ʌ と同じでも、ɪ と同じでも良い。後者ならほぼほぼ日本語の「え」。例) lemon /lɛ́m.ən/ レモン → ə は ɪ で良い。 pivot /pɪ́v.ət/ 軸を中心に回転する → これらの ɪ と ə はアメリカ発音の音声では同じになっている。
→次は「発音記号」から「発音リスペリング (pronunciation respelling)」へ (ブログの記事になっています)
「ə シュワー (schwa) シリーズ」
→英語の発音記号/ə/の読み方、レベル1初級者編:99%の人が犯している発音ミス
こちらのYouTubeでも解説していますので、是非ご覧ください。
本気で発音記号をやりたい人はこちら。